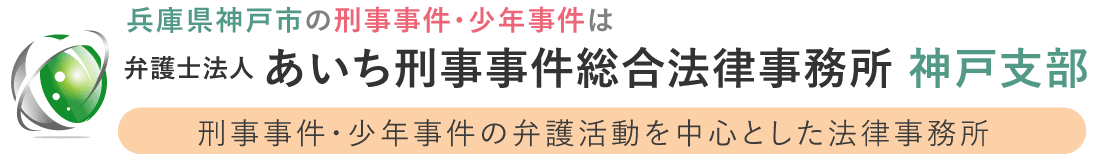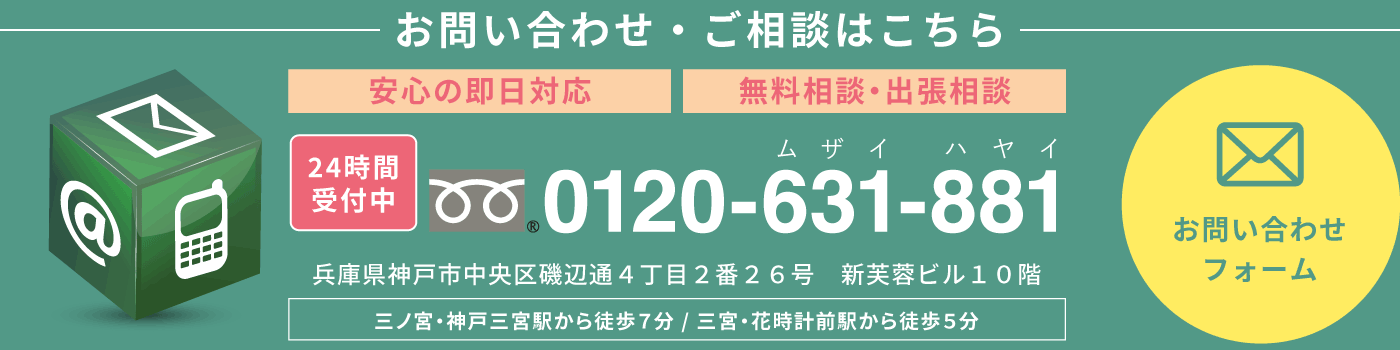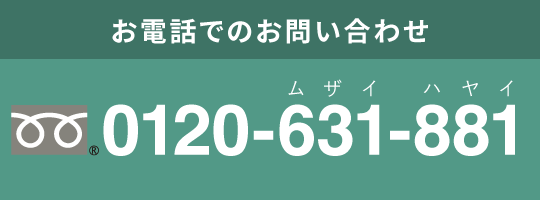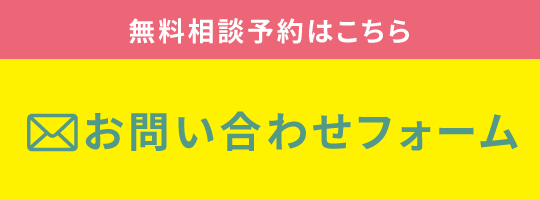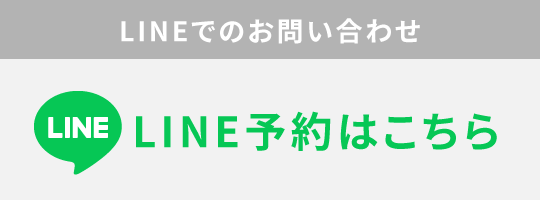※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。
【殺人罪】
「人を殺した」場合、「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」になります(刑法199条)。
殺人罪は、文字通り人を殺した場合に問われる罪です。
人の生命に対する侵害ということで、最高刑には最も重い死刑が規定されています。
とはいえ、法定刑の幅は広く、事件ごとに個別の事情が量刑事情として考慮されます。
殺人罪が適用されるには、人を殺すという意図(殺意)をもって行った暴行により被害者を死に至らしめたことが必要です。
ですから、被害者を殺害するつもりまではなく、結果として死亡させてしまったような場合には、傷害致死罪や(重)過失致死罪が適用されるにとどまり、殺人罪は成立しません。
殺意の有無を判断するポイントとしては、創傷の部位・程度、凶器の性状・用法、犯行前及び犯行時の犯人の言動、犯行後の行動、動機等を総合的に考慮して判断されます。
したがって、殺意の有無を争う場合には、犯行時や犯行前後の客観的状況から、殺意を持っていなかったことを主張していく必要があります。
検察官は、解剖医や鑑定医等を証人として呼び、創傷の部位や程度から、犯行態様が明らかに殺意を持ってしたものであるとの主張をしてきます。
このような場合、個別の事件によっては、弁護側からも別の鑑定医に依頼し、証人となってもらうことで検察官が主張する犯行態様とは異なるということを主張していくことも考えられます。
公判で殺意がないことを主張する場合、それを基礎づける証拠の収集と訴訟戦術はまさに弁護士の腕の見せ所です。
また、殺人という重大事犯であることから、捜査機関による捜査にも熱が入り、執拗な取り調べを行うこともあります。このとき、違法な取調べが行われないよう弁護士に依頼して、捜査機関に抗議してもらうことも大切です。
刑事弁護は、犯罪をしたものに刑罰を科す手続きですから、厳格に行われなければなりませんし、誤りがあってはなりません。
特に殺人事件のような場合には、厳しい処罰が予想されますから、取り返しのつかないことになってしまいます。
殺意の有無を争い、殺人罪の成立を阻止するためには、刑事裁判の経験が豊富な弁護士に依頼するのがベストです。
殺人罪と関連する犯罪
殺人予備罪(刑法201条)
人を殺す目的で「その予備をした」場合、「2年以下の拘禁刑」になります。もっとも、情状により刑を免除することも可能です。
自殺関与罪(刑法202条)
「人を」「教唆しもしくは幇助して自殺させた」場合、および「人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した」場合、「6か月以上7年以下の拘禁刑」になります。
~殺人事件における弁護活動~
捜査機関は殺人事件という重大事犯であるとして早期解決に躍起になり、あなたを犯人であると決めつけて、強引な取調べや捜査を行うかもしれません。
そんなときは、違法な取り調べが行われないよう警察や検察に働きかけたり、虚偽の自白や不利な調書が採られないようにしたり適切な取調対応をアドバイスします。
また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、殺人罪として起訴・有罪にするには証拠が十分にそろっているとは言えないことなどを主張したりします。
逮捕など身柄拘束されている状態でこうした活動をすることは不可能ですし、そうでなくとも一般の方が行うには、かなりの困難が伴います。
そのため、一般的には弁護士を通じてこれらの弁護活動を行うことになります。
殺意がないことの主張
殺人罪が成立するためには、前述のようにわざと人を殺したという故意、つまり、殺意が認められなければなりません。
しかし、故意は人の内面である主観を問うものですから、検察官による立証が難しいのです。そのために、刑事事件では故意の有無がしばしば争点になります。
特に殺意のような強烈な意識があったことを立証するのは困難を伴います。
殺意の有無は、死因となった傷の部位、傷の程度、凶器の種類・使用方法、動機の有無、犯行後の行動など様々な客観的状況を総合的に考慮して判断されます。
そこで、弁護士はこれらの事情を詳細に検討し、殺意の存在と矛盾する点があれば、その点を強く訴えていきます。
因果関係がないことの主張
犯罪が成立するには、行為と結果との間に因果関係がなければなりません。
殺人罪でも同じです。
つまり、加害者の行為によって、加害の相手方が死亡することとなったという一連のつながりが認められなければなりません。
因果関係が否定されれば、犯罪が成立することはありません。
殺人事件の弁護では、本当に被告人の殺害行為によって被害者が死亡したのか疑わしい場合、第三者の行為が介在しているような場合、その点を徹底的に追及します。
正当防衛・緊急避難の主張
殺人事件でも、自己または家族など大切な人への攻撃に対する反撃としてなされた場合、あるいは自己または家族などを守るためやむを得ず第三者を傷つけてしまった場合があります。
こんな場合は、殺害行為が正当防衛・緊急避難行為に当たるとして正当化される可能性があります。
したがって、弁護士としては様々な客観的状況や目撃証言を収集し、加害者の行為が事件当時やむを得ない行為であったとして正当性を主張していきます。
情状弁護
前述のように、殺人罪の法定刑は非常に広範です。
事件を起こしてしまったことについて全く争いがない場合でも、酌むべき事情があれば、刑が軽くなる可能性があります。
犯行に至った経緯や動機、犯行後の状況などに鑑みて、裁判員や裁判官が同情できるような事情を主張立証していくことが可能です。
これを情状弁護と言います。
個別の事件によっては、執行猶予付きの判決が認められることもあります。
弁護士は、犯行前後の経緯や状況を綿密に調べ、例えば介護疲れ・心中崩れなどの事情があれば、それを強く訴え減刑又は執行猶予付きの判決を目指します。
~どんな場合に成立するか~
|
ケース その後、神戸市東灘区にある神戸港において、AはBに車ごと海に飛び込むよう命令しました。 もっとも、当時は真冬であったうえ現場の状況では、たとえ脱出の意図があってもBが死亡する危険が非常に高いものでした。 |
Aの行為は、何罪に問われるでしょうか。
Bの行為は、客観的にみれば自殺ですが、B自身には自殺する意思はなかったのですから、Aに自殺関与罪は成立しません。
では、Aの行為は、殺人罪に問われうる行為と評価できるでしょうか。
Bは、Aに命令され、死ぬつもりはないのに海に飛び込むという死の危険の高い行為をしました。
このとき、Bの精神状態が、Aの命令に従い車ごと海中に飛び込む以外の行為を選択することができないというものであった場合には、AがBに命令した行為は、Bを死亡させる危険の高い行為であるといえるでしょう。
したがって、この場合、Aの行為は、殺人罪にあたる行為をしたと評価することが出来ます。
また、Aは初めからBを死亡させるつもりだったので、殺意に欠けるということもありません。
ただし、結果としてBは死亡しなかったわけですから、Aには殺人未遂罪が成立することになります。
|
ケース Aは、最初戸惑ったもののしぶしぶ了承し、二人で毒入りジュースを飲んで心中する運びとなりました。 |
殺人事件の場合、注意しなければならないことは予備罪の規定があるということです。
予備とは、すなわち準備をすることです。
殺人罪は、人の生命を奪うという重大な犯罪なので、人を殺す目的でその準備をした場合も罰するのです。
自殺幇助罪は、他人が自殺するのを手助けした人を罰する規定です。
心中を申し出たのはBであることから、Aは毒入りジュースを飲ませることでBの自殺を手助けしただけではないかと思われます。
しかし、同様のケースで裁判所は、殺人罪の成立を認めました。
その理由は、AとBが心中しようとした時点において、すでにAは自殺する意思がないにもかかわらず、その意思があるように見せかけてBに毒入りジュースを飲ませたからです。
つまり、今回のようなケースでBはAが追死すると思ったから自殺したと考えられるところ、実際はAに騙されていたということからすると、もはやBの行為は自殺と認定できないというのです。
むしろ、AがBの行為を利用して、Bを殺害したと結論付けたわけです。
始めから自殺させるつもりで致死量を超える毒を準備していることから、Aに殺意があることは明らかでしょう。
したがって、Aには殺人罪と殺人予備罪が成立するといえます。