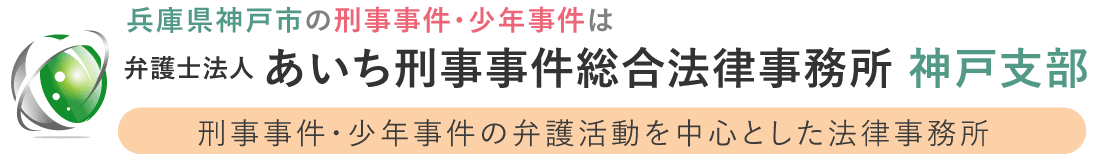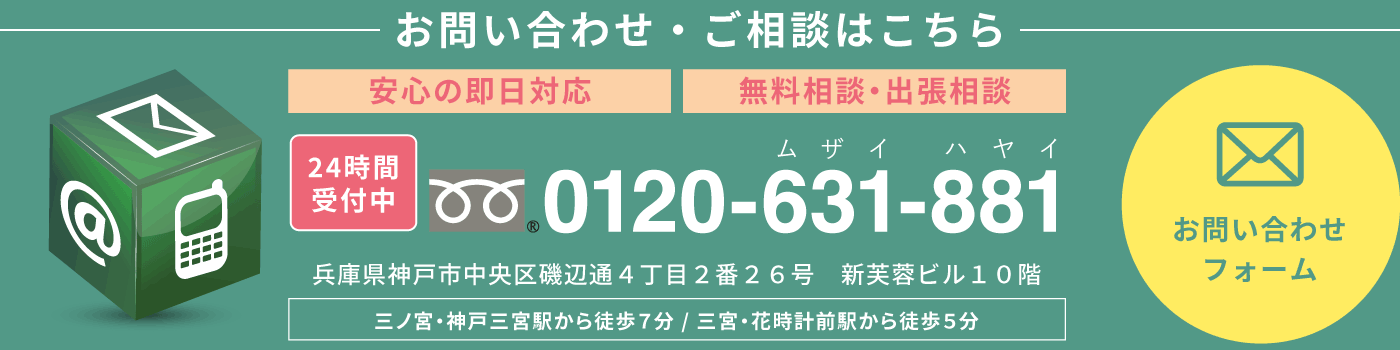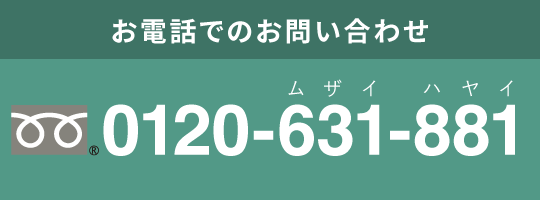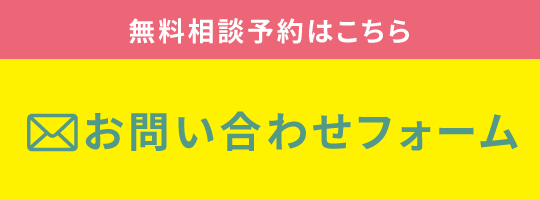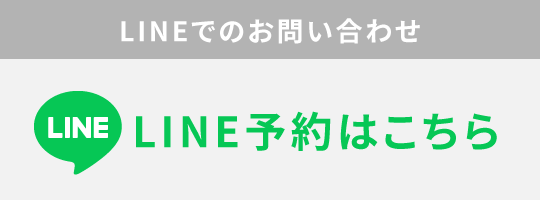窃盗罪の間接正犯が成立する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
生活に困窮していたAは、自身の子供であるB(12歳)に、兵庫県南あわじ市の資産家で有名なVさんの家に侵入して金品を盗ってくるよういいました。
Bは、そんなことをしても捕まるだけだと思い嫌がっていたところ、Aが「あの家は老人しかいないし、耳も遠いから気づかれにくいから大丈夫。」と言ったところ、Bは渋々納得しました。
Bは、深夜の方が住人が寝ているから気づかれないこと、マスクを被っていれば万が一住人に見つかっても身元は割れないこと、侵入や窃盗の方法については自らネットで検索して入念な計画を立てて、実行に移しました。
事件から数か月して、兵庫県南あわじ警察署は、Bの犯行であることを突き止め、Bを保護しました。
警察は、Aについて窃盗の容疑で逮捕しました。
(フィクションです)
間接正犯とは
「間接正犯」というのは、他人を道具として利用することにより犯罪を実現する場合をいいます。
自分は直接手を下さずに、他人を使って犯罪行為を実行することですが、直接正犯と同じく、正犯として処罰されます。
犯罪であるというためには、問題となる行為が「構成要件に該当する、違法で有責な行為」でなければなりません。
犯罪の成立要件のひとつである、問題行為が構成要件に該当する(=構成要件該当性)と言える場合は、行為者が実行行為を自ら行い、結果を生じさせた場合のみならず、実行行為を他人に行わせ、その他人によって結果を生じさせた場合も含まれます。
間接正犯が成立する要件は、次の通りです。
①実行行為-(a)他人を道具として利用し、自己の犯罪を実現する意思を有すること。
(b)被利用者を一方的に支配・利用し、その行為を通じて構成要件的行為を行ったこと。
②因果関係
③故意
間接正犯の成否が問題となる場合
どのような場合に間接正犯が成立するのか、以下、問題となる類型ごとに見ていきます。
1.事理弁識能力や意思を抑圧されている者の利用
間接正犯の実行行為性の有無については、「他人を一方的に利用して犯罪の結果実現過程を支配した」といえるか否かによって判断されます。
そのため、行為者が意思能力を欠く者を使って犯罪の結果を実現させた場合には、その者を思うがままに利用したといえるため間接正犯は成立すると理解されます。
また、心神喪失者のような責任能力を欠ける者の行為を介在させる場合も、この者が是非弁別能力にかけるときは、同様に間接正犯が成立するとされます。
一方、判例は、被利用者が14歳未満の刑事未成年である場合であっても、是非弁別能力があるときには、意思の抑圧などの事情が存在しない限り、間接正犯の成立を肯定することはできないとの立場をとっています。
(1)被利用者の意思が抑圧されている場合
被告人Xは、12歳の養女Yに対して日頃からXの言動に逆らうそぶりを見せるたびに、顔面にたばこの火を押付けたりドライバーで顔をこすったりするなどの暴行を加えて、自己の意のままに従わせていたYに対し、窃盗を命じてこれを行わせた事件について、最高裁は、Xが自己の日頃の言動に畏怖し、意思を抑圧されているYを利用して窃盗をおこなったと認められるため、たとえYが是非善悪の判断能力を有する者であったとしても、Xについては窃盗の間接正犯が成立すると、窃盗罪の間接正犯を成立を認めました。(最決昭58・9・21)
(2)間接正犯が否定された事例
X(Yの母親)が生活費欲しさから強盗を計画し、12歳10か月の長男Yに指示命令して強盗を実行させた事件において、当時Yには是非弁別能力があり、Xの指示命令はYの意思を抑圧するにたる程度のものではなく、Yは自らの意思によりその実行を決意した上、臨機応変に対処して強盗を完遂し、Yが奪ってきた金品をすべてXが領得したなど判示の事実関係の下では、Xにつき強盗の間接正犯または教唆犯ではなく共同正犯が成立すると、強盗罪の間接正犯の成立を否定した判例があります。(最決平13・10・25)
この事例を踏まえて、上記ケースにおいてAについて間接正犯が成立するか否かを検討してみましょう。
Bは、Aから、侵入盗を行うよう命令指示されたところ、「見つかって捕まるからいやだ」と拒否しています。
このことより、Bは、「侵入盗」が犯罪であること、犯罪をすれば逮捕され得るということをきちんと理解していると考えられ、是非弁別能力はあったものと言えるでしょう。
そして、侵入盗について許否したBに対して、Aが「老人だから大丈夫」といったことを伝えたところ、渋々ではあるけれどもBは侵入盗を実行することに納得したのですから、Aの指示命令はBの意思を抑圧するようなものではなく、B自らの意思に基づいて実行を決意したものと考えられます。
さらに、Bは綿密な犯行計画を練った上で実行に移していることをも考慮すれば、Aに対して窃盗・住居侵入の間接正犯が成立するものとは言えないでしょう。
しかしながら、Aに対してこれらの罪の共同正犯が成立し得ると考えられますので、Aが同罪の正犯となることには変わり有りません。
実際に自ら犯罪行為に着手していない場合であっても、正犯として刑事責任を問われる場合もあります。
窃盗事件で被疑者として取調べを受けている、家族が逮捕された、と対応にお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。